布団楽車・獅子太鼓などで、広島県無形民俗文化財にもなっている、氏神である常磐神社の春の祭りが盛大に行われます。今年の開催日は、3月23日(土)・24日(日)の2日間です。
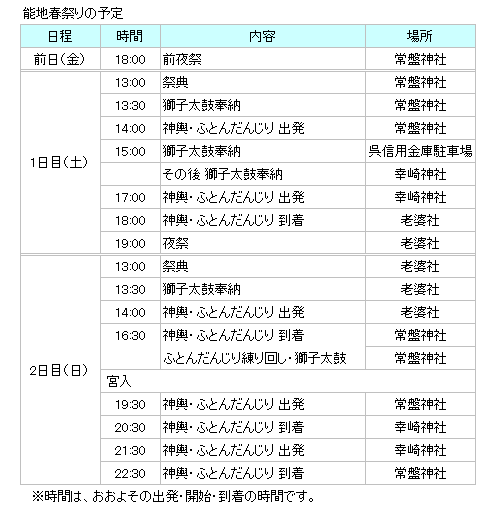
詳しくは → http://mihara-kankou.com/festival/noujiharumatsuri.htm
 三原市幸崎町能地(のうじ)は、古来より漁業で栄えた町で、その記述は日本書記にもみられ、瀬戸内海漁業の発祥の地とも伝えられている。ここで、毎年行われる「浜の祭り」は、常磐(ときわ)神社の春祭りで、豊漁を願う勇壮な祭りとして知られる。 三原市幸崎町能地(のうじ)は、古来より漁業で栄えた町で、その記述は日本書記にもみられ、瀬戸内海漁業の発祥の地とも伝えられている。ここで、毎年行われる「浜の祭り」は、常磐(ときわ)神社の春祭りで、豊漁を願う勇壮な祭りとして知られる。
能地の漁業は、今はまったく姿を消した家船(えぶね)とよばれる住まいを兼ねた打瀬船で、九州や讃岐方面にまででかけるというもの。一年のほとんどを船の上で過ごす人々も、この祭りに先駆ける旧正月14日の神明祭りまでには必ず帰り、賑やかな祭りを行っていた。
祭りはまず神明祭で、世話人である「当家(とうや)」を決めるくじ引きから始まる。それから当家を中心に旧正月27日、28日(平成5年から3月の第4土、日曜日)の祭り当日にむけて、1〜4丁目の各町内から出される四つの「ふとん楽車(だんじり)」の準備、楽車に乗り太鼓を打つ8人の神童の決定、その稽古と準備が進められる。
祭りは、御神体をのせて、常磐神社を出発した神輿が町の氏神幸崎神社(東の祭)へ行き、御神体を迎え、二神となってその夜を御旅所となる老婆(うばく)社で明かし、翌日、常磐神社(西の祭)に向かって進む、見所は、何と言ってもこの渡御(とぎょ)する神輿を挟む4つの楽車の激しい練り合いと要所要所に奉納される「獅子太鼓」である。
楽車(だんじり)を使うようになったのは、天保から明治にかけての頃、伊予新居浜の辺りに出漁していた者が見て帰ったのが始まりと伝えられる。楽車には、5歳〜8歳くらいの化粧をされ着飾った男の子が神童として乗り込み、太鼓を打ち続け、町内の若者たちがそれを肩に担いだり引っ張ったり、時には楽車同士がぶつかり合って練り合いをする。その練り合いの激しさは、渦潮にのる船の様子を表わし、勇壮で男らしい迫力のあるもので、時に、通りの家の軒先を壊すこともある。
「獅子太鼓」は平和と五穀豊穣(ごこくほうじょう)、大漁を祈願して奉納するもので、8人の神童によって行われる。三十八手(以前は四十八手あった)打手があり、ちゃんぎりや笛、獅子舞も加わり、軽快な中にも優雅さを備えたリズムで、神楽の音ではなく雅楽の流れをくみ、日本でも珍しいといわれている。昭和49年、三原市の無形文化財に指定された。
獅子太鼓保存会の結成、幸崎中学校郷土芸能クラブの設立など、住民が一体となってその伝承に務めている。
|